■ 損益計算書の基本構造
損益計算書は、会社が一定期間(通常1年間)のうちに、いくら儲けたか、あるいは損をしたか、つまり利益がどう生み出されたのかがわかる書類です。
損益計算書の基本構造は、下記のようになっています。
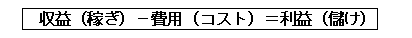
この基本構造をさらに詳しく示したものが、下記の図です。
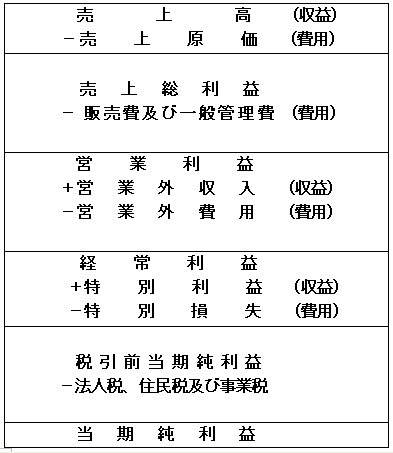
■ 損益計算書の利益は5つ
損益計算書には、以下のとおり、 売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益 という5つの利益があります。そして、この中で最も重視すべき利益が 「経常利益」 なのです。
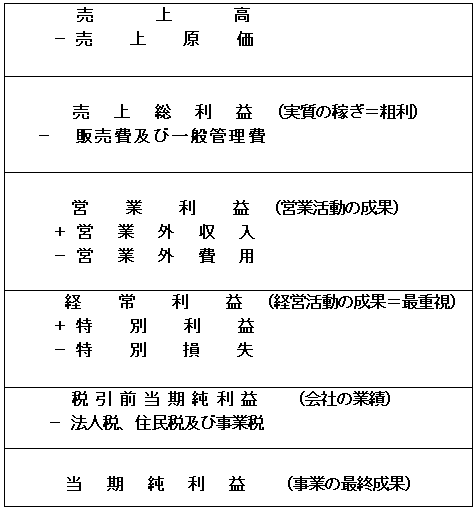
■ 変動損益計算書に変える
なぜ変動損益計算書に変えるのか?
損益計算書を読みこなそうとするときに、そのままの損益計算書で見るのではなく、 「変動損益計算書」 という形に変えて読みます。
では、なぜそのままの損益計算書ではダメなのでしょうか? それには理由があります。たとえば、ある会社の損益計算書の経常利益が50万円だったとします。しかし、それだけでは利益の絶対額がわかっても、それ以上のことは何も判断がつきません。
すなわち、会社を経営する社長の視点で見ると、 同業他社に比べ、その利益を見て儲かっているのかどうか、そして儲かっていないとすれば、どこをどう変えたら良いのか ということまで明確にわからなければ、経営上意味がないということです。
従って、経営という実務上の判断を明確にするために 変動損益計算書 に変えて読むことが必要となってきます。そして、利益の「絶対額」ではなく、 「比率」 で見るようにしましょう。こうすることによって、売上の規模に関係なく、同業他社との比較が可能となります。
■ 変動損益計算書とは?
変動損益計算書とは、どのようなものでしょうか。
変動損益計算書の基本構造は下記のように表されます。
売上高-変動費=限界利益 (簡単にいうと粗利のこと)
限界利益-固定費=経常利益
損益計算書と比較すると基本構造が以下の図のようになります。
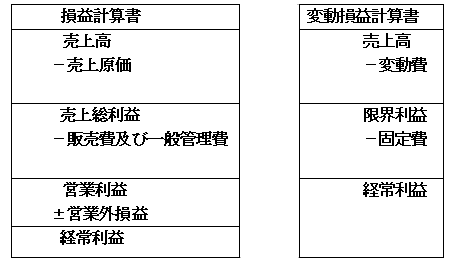
【 イメージ図 】
損益計算書を変動損益計算書に変えることで、損益計算書が経営に活用しやすくなります。
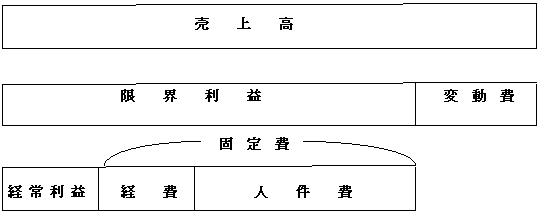
■ 究極の指標 経営安全率(損益分岐点比率)に注目する
① 損益計算書では何よりも「経営安全率」に注目します。
経営安全率は、 「経常利益÷限界利益(売上高-変動費)」 で求められます。これは、限界利益に占める経常利益の割合です。
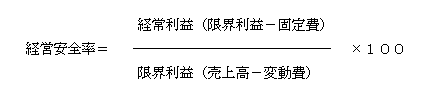
② 「○%売上落ちても損益トントン」
会社を経営していくうえで、必要とする利益を確保するためには、どのくらいの売上が必要になるかを知る必要があります。逆に言えば、自社は売上高の減少にどのくらい耐えられるかということです。
経営安全率は、 「○%売上落ちても損益トントン」 (マイナスの場合、売上が○%上がると損益トントン)という数値で、会社の業績を把握することが出来ます。
この結果、会社の規模に関係なく、同業他社との比較が可能となります。社長の会社と上場企業との比較も可能になるのです。
③ 経営安全率の目標は15%
赤字企業、黒字企業、優良企業(黒字企業の上位15%)の経営安全率を比較したところ、赤字企業の平均は-7%(売上が7%伸びると損益トントン)、黒字企業の平均は8%(売上が8%落ちると損益トントン)、また、優良企業(黒字企業の上位15%)の平均は18%、すなわち、(売上が18%落ちると損益トントン)になることがわかりました。
経営安全率が高いほど余裕があり、得意先がカゼを引いたときの売上減に耐えられます。 目標は15% です。
④ 経営安全率の逆が損益分岐点比率
当社は限界利益(粗利益)で固定費を賄いきれているのか?と心配になられる社長もいらっしゃることでしょう。その場合は、 損益分岐点比率 に注目です。損益分岐点比率は、 「固定費÷限界利益(売上高-変動費)」 で求められます。これは、限界利益に占める固定費の割合です。
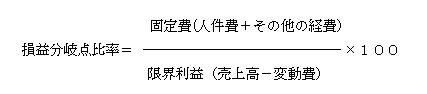
⑤ 損益分岐点比率の目標は85%
損益分岐点比率が100%でちょうど損益トントンです。儲けた利益をちょうど全て使い切っておしまいという状態です。儲けた利益はどこへ消えたか?人件費や賃借料などにきれいさっぱり使い切ってしまいました、ということになります。
では、目安はどの位か? これも赤字企業、黒字企業、優良企業(黒字企業の上位15%)の損益分岐点比率を比較したところ、 赤字企業の平均は-107%、黒字企業の平均は92%、また、優良企業(黒字企業の上位15%)の平均は82%になることがわかりました。 経営安全率とは逆に低ければ低いほど良いのです。
損益分岐点比率が低いほど経費が賄いきれており、売上減に耐えられます。 目標は85% です。
■ 経営安全率を高めるための2つの工夫
① 限界利益アップ
「売上高-変動費=限界利益」
限界利益は、上記算式により計算され、さらに分子の経常利益は、 「限界利益-固定費」 で計算されるため、経営安全率を高めるためには、限界利益を高めることが必要です。これは多くのお客様のお役に立って、かつ値が通って喜ばれたことにほかなりません。
② 固定費をコントロールする
会社の経費は売上に比例する変動費と、比例しない固定費に分けることが出来ます。そして、ぜひとも押さえて欲しいのは、 「固定費こそ赤字経営の原因」 という事実です。固定費が0の会社は経常利益がマイナスにならないからです。
さらに、固定費のなかで最大のウエイトを占めるのが人件費です。これは何も給与や賞与以外に、社会保険料の会社負担分などの費用も含めて考える必要があるのです。
さらに敢えて理想を言わせて頂きますと、 人件費は限界利益の50%、その他の経費が35%で、経常利益が15%です。 あまりビックリしないで下さいね。
■ まとめ
① 損益計算書は、 一定期間(通常1年間)における企業の業績(儲かったのか、あるいは損したのか)を明らかにする書類 です。
② 損益計算書には5つの利益が表されますが、最も重要なのが 「経常利益」 です。
③ 損益計算書は、 「変動損益計算書」 に作りかえて読んでいきます。
④ 経常利益は、限界利益(売上高-変動費)-固定費で求められます。そこから 経営安全率 (限界利益に占める経常利益の割合)を求めれば「儲かっているの?」の利益面での業績がわかります。

⑤ 利益は絶対額で比較してはいけません。 経営安全率で比較しましょう。 ○%売上が落ちても損益トントンという意味で大きいほど好ましいです。また、経営安全率の逆が損益分岐点比率です。損益分岐点比率は小さいほど好ましいです。
⑥ 経営安全率を高めるためには、 「限界利益を上げる」 、 「固定費(人件費とその他の経費)をコントロールする」 という2つのアクションがあります。